
蒲団・一兵卒 (岩波文庫)
主人公の時雄は非常に情けない男だ。
芳子の気持が田中にあると知ると、酒を飲んで細君に当り散らし、実家の父親にまで手紙で告げ口をする。
家庭を壊してまで、芳子と一緒になる気は毛頭ない、とても気の小さい男だ。
それに加えて芳子を見送る場面では、「細君さえいなければ芳子と結婚したに違いない」と自意識過剰な所もある。
物語自体もあまり抑揚がなく、個人的には『田舎教師』の方がいい作品だと思う。
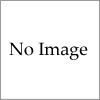
一兵卒の銃殺 (岩波文庫)
主人公―要太郎が兵営を脱走する場面から舞台は幕を開ける。要太郎は酒と女に溺れ、どら息子として描かれている。また、彼は終始一貫して社会に反抗的な態度を取る。そして、そんな彼は最後には到底許すことが出来ない事件を引き起こす。
このように評すると、一見要太郎は、自己閉鎖的で自分本位な主人公だと思われる。確かにそうなのだが、しかし著書の本質はそこにあるのではない。彼がなぜそのような暴挙にでたのか。その根底にあるものはなんなのか。つまり、本書の本質は、彼がそのような人間になった背景には「社会の責任」が存在するということである。
著者は、彼を人間的に教育できなかった社会に対して疑問を投げ掛けている。教育が叫ばれる現代社会にも相通じる所があるはずだ。要太郎は終始悪人として描かれているが、彼が事を起こす際には必ず葛藤している点に注目して欲しい。本当は人間として真っ当に生きたかったことだろう。そんな彼には、人間の儚さを感じずにはいられない。
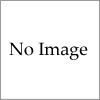
蒲団・一兵卒 (1972年) (岩波文庫)
これまではテキストを読むこともなく、文学史に関する断片的な知識のみで『蒲団』(1907年発表)イコール自然主義/私小説イコール中年男(主人公である竹中時雄)の性欲描写みたいな図式を鵜呑みにしてきましたが、今回初めて一読、どうしてどうしてこれは中年男のプラトニック・ラヴを描いてある意味極めて直截かつ瑞々しい傑作であると感じ入りました。徳川時代の遺風として未だ男子(家長)としての体面や面子が重んじられていたであろう当時の日本社会において、これだけの心情暴露をなすというのは大いに勇気の要ったことでしょうし、そうした因習との対決的緊張感が全編に一本の「芯」を与えているようにも感じます。(即ち、テキストを読まずしてイメージだけで論ずることの無意味さに、改めて気づかされました。)
併せて収録されている「一兵卒」(1908年発表)も脚気衝心で日露戦争の戦場に落命する一兵士の姿を描いて悲痛。この当時、このような反戦小説(と云ってもよいでしょう)が書かれていたことにもある意味驚かされました。






