
落合博満 変人の研究
一般的に嫌われ者で、常にダーティーなイメージのあり、最も監督から遠いと思われていた落合が中日ドラゴンズの監督になり、日本一位にまでなった。野球エリートばかりのプロ野球界において、全く異質な経歴を持ち独自の方法で進み、周りと対立しながらもしっかりと結果を残し続けている。
ねじめ正一がいろんな人達の対談や自分の言葉達を使い、そんな落合についての詩を編んでいるような本だ。
レビューを見ると賛否両論のようだが、私にはとにかく面白かった。
落合については異端児というイメージがあるが、実は純粋に
・投げて
・打って
・取って
・走って
という面白さの原点を大切にし、その気持ちをじっくりと育てその中で選手達を鍛え、育てているということがよく分かる。
プロ野球は、とにもかくにも価値を決めるのが「お金」という一つの基準だけになってしまい、お金のある巨人が大金をばらまいて有名選手を集める。
そんな手法がまかり通っていることが、野球本来の魅力をなくし結果として、人々は野球から離れて行ってしまう。
野球を楽しみ、野球で勝負するのではなくなってしまっているのだ。
その原因を作ったのは、落合、という印象があったが、それはこの本を読んでみると、印象とはまた違った事実が分かってくる。
野球が本来持っている楽しさ。それは、なかなか言葉や数字にするのは難しい。
でも、落合は自分のプレーで、そして監督として選手にそれを伝えそして中日は強くなった。
「面白さの原点を大切にする」ということの大切を教えてもらった気がする。

うがいライオン (チューリップえほんシリーズ)
動物園のライオンくん。自分はライオンだから、ライオンらしくあらねばといつもがんばっているけれど、とうとう疲れて、わざとライオンらしくないことなどをしてみるけれど、それで受けすぎると、それもなんだか困ってしまって、またがんばってライオンらしくあろうとするけど、それだと受けなくなってしまって…。
ねじめの「笑い」を長谷川がどう「笑い」絵に仕立てているかを堪能してくださいね。(ひこ・田中)

荒地の恋 (文春文庫)
実名小説ということで雑誌のゴシップ記事に対するのと同じような興味があったのだが、薫りたかい作品に出合えてよかった。
本の紹介に「親友の妻と恋に落ちた時、彼らの地獄は始まった」というとおり話は北村太郎と田村隆一の妻明子との関係を中心に進んでゆく。
しかし僕には「恋に落ちた」こと自体が感覚として納得できない。もちろん五十になっても六十のなっても心には瑞々しいところがあるから異性を惹かれたり好きになったりすることはあるだろうが、その様な心の動きを否定はしないまでも統制はするというのが妻子がいるという状況を作った人間としての責任だろうと思う。というように考えるのが僕のような散文的な人間であって詩人は「恋に落ちる」のかも知れない。
僕にとっては、明子との関係より阿子との関係のほうが生々しく実感できる。性的な描写があるから生々しい実感があるのではなく、多発性骨髄腫という有効な治療法のない病をえた六十すぎの男の心の在り様がわかる。もちろん、阿子と知り合った時点では病気は存在していなかったが、阿子に傾斜してゆく心の動きのほうが明子と「恋に落ちる」よりずっと共感できる。
時が流れ六九歳で死去。
結末に阿子の視点で語られる部分があるのがいい。
最後の4行が鮮烈。

ぼくらの言葉塾 (岩波新書)
長く「ことば」をなりわいにしてきた方だからこそ書けたであろう、エッセイ・アンソロジー。
歌、詩、俳句から例をとり、豊富な経験と独自の感性から言葉の味わい方、楽しみ方を縦横無尽に語りつくす。
「自分の言葉を発見する」「言葉の関節を外す」「こわして作る」「声で遊ぶ」など、ポイントというかコツを一つ一つ伝授。
単なる形式や理屈では伝わらない、ハートにじわじわ響く言葉の使い方が浮かび上がる一冊だ。
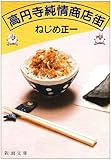
高円寺純情商店街 (新潮文庫)
ミステリーやサスペンス小説は読者が非日常の浸れるから人気があるのだと思うが
やはり人が殺されすぎる
ある人物を登場させて、その人物の背景を丹念に書き上げ
そして、殺す
読者としては、感情移入し、きっとこの人は殺されてしまうんだろうと
思いつつ、読み進めて、案の定の結果となり、ジェットコースターに乗っている
ような感触に酔う
これが本を読むことだとしたら、とても切ない行為だ
それに比べてこの小説
なんとものんびりして、大きな展開はない日常的な生活をたんたんと
書き連ねてある
いつのまにかその世界に入ると
小さな事件が、逆に世界がひっくり返るような事件に思えてくる
化粧品屋のきれいなお姉さんたちはどうなるのだろうか
あげくには、商店街での火事騒ぎ
殺人事件に比べれば、はるかにささいな出来事だが
筆者の巧みな描写で、ひとときだけ「純情商店街」の住民になれる
ありふれた日常を書きながら、逆にありえない「平凡な日常」を堪能できる作品
現代人にとって、かえってそれが「非日常」なのかもしれない






